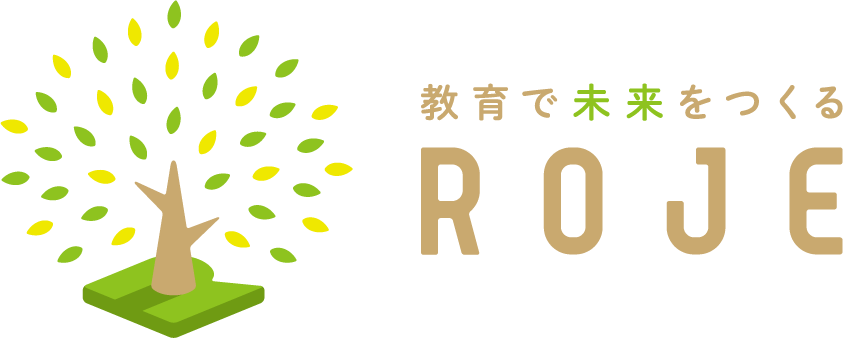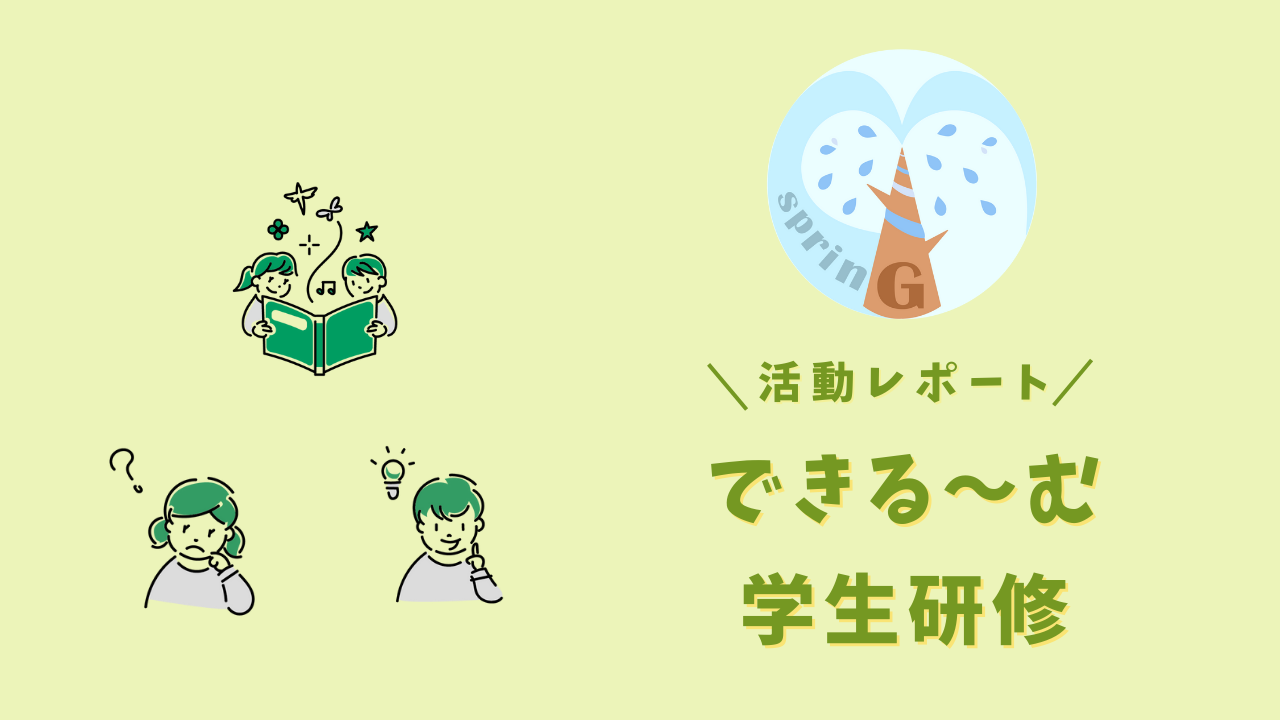こんにちは。
ギフテッドプロジェクトsprinG社会人スタッフのラナです。5月に行った学生研修の様子をお知らせします。
▶前回の様子はこちら
今回のテーマは
「できる~むの雑談について」
12月にも話し合ったテーマではありましたが、4月に入り、参加する子どももスタッフも状況が変わっていく中で、再度検討をすることになりました。
できる~むでは「雑談」というスペースを設けています。
子ども数名に対してスタッフ1人が入って、特に決まりはなくおしゃべりをします。
できる~むに慣れてきたからこそ、安心安全であると思ってくれているからこそ、ゲームというコンテンツを介さずに、もっとストレートに「相手のことが知りたい」「自分を知ってほしい」という気持ちで参加してくれる子が多いのかもしれません。
はじめは、「自分の話を聞いてほしい!」という子が多く、話題が特定の子どもに偏らないように、または話題が合わず沈黙にならないように意識していました。
しかし最近は、「誰かの話を聞きたい」「作業をしながらなんとなく話をしたい」という子が多い印象です。
そうなると、話題をどう作るか、話しやすい空間をどう作るかがスタッフの課題となってきます。
そういった場面でのスタッフ対応を改めて検討しました。
結論としては以下のようになりました。
1.安心安全である空気づくりを徹底すること。
2.トークテーマを作ってみること。
3.話題の振り方を意識すること。
以下、話し合いのほんの一部になりますが、具体的にお伝えします。
安心安全である空気づくりを徹底すること。
「面白いことを話さなければならない」とか「みんなが興味のあることを話さなければならない」、「間違ったことを伝えたら恥ずかしい」と考えていると、大人も発言しにくくなるものですよね。声馴染みとはいえ、顔や年齢もわからない人たちと、できる~むで話すとなるとなおさらです。
だからこそ、スタッフが率先して「オチのない自分の話をしてもいいこと」や「言葉が閊えて無言になってもいいこと」や「わからないことはその場で調べてみて話せばいいこと」などを体現していきたいという話になりました。
もちろん、「話したくないことは無理に話さなくていい、聞かない」という部分はできる~むの共通認識です。
話すきっかけを作ってみること。
「相手のことが知りたい」「自分を知ってほしい」とは思うけれど、何を話していいかわからない、または話したいことがあるけれど、それを切り出す勇気はない。そんな場面もあると思います。
そこで、いくつか「話し始めのきっかけづくり」ができる案を出してみました。
例)自己紹介から始める、トークテーマを事前に集めてどれがいいか決める、好きなものについて語ってもらう。
また、音声ではなく文字のチャットのみでコミュニケーションを取る子もいますので、自己紹介などをすることで、そういった子も(本人がつらくない範囲で)巻き込めたらいいなと思っています。
話題の振り方を意識すること。
先述した通り、できる~むには、チャットのみでコミュニケーションをする子もいます。また、話を聞きたいだけで(その時は)自分の話をしたくない子もいます。
誰かが置いていかれることがないように、または無理をしなくていいように、話を振ったり振らなかったりすることの重要性についても検討しました。
実際の場面では、当日まで子どももスタッフも、どんな組み合わせになるかわかりません。
よって、まだまだうまくいかないことも多いとは思います。しかし、安心安全な居場所であることを守りつつ、スタッフはもちろんのこと、こどもたちと一緒に、試行錯誤しながら「できる〜む」を作っていけたらと思っています。
執筆者:ラナの感想
まずは、子どもたちから、「ゲームではなくおしゃべりがしたい!」という声が増えてきたこと自体、できる~むの在り方への転機になるように思えます。
ゲームで競いあったり協力しあったりするのは、もちろんコミュニケーションを取る上でも、できる~むに自分が「居ていいんだ」と思えるためにも、重要です。
一方で、「(ゲームや会話で)必ずしも誰かの役に立たなくても居ていい」と思える「雑談」という空間の需要が高まっていることは、大きな意味があるように思えるからです。
ルールが決まっていて話さなくても輪に入れるゲームもある、自由度が高い分みんなでも一人でも遊べるマインクラフトがある、そしてもっと自由度高く話せる雑談がある。こうした状況を、無理ない形で維持していきたいと個人的には考えています。
また、研修の中で印象的だったスタッフの発言があります。
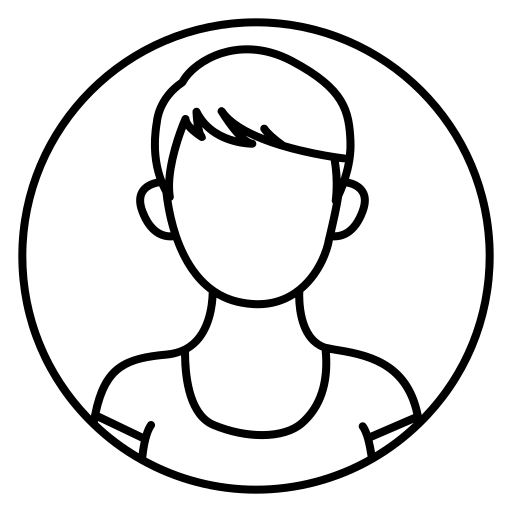
「無言でもいい」
「うまく話せなくてもいい」
「私(スタッフ)も雑談苦手だけど好き」
どれも、こどもたちの「雑談の場に居たいけど、うまく立ち回れなかったらどうしよう」という不安に寄り添っているものだと思いました。
だからこそ、スタッフ自身が身をもってそれを表現していこうという様々な案が出たのでしょう。
「どんな話も面白おかしく変えてくれる司会者」のようなスタッフはなかなかいませんが、それは日常生活でも同じことです。どのコミュニティにいても、雑談というツールを使うには、練習やちょっとの勇気が必要です。
子どもたちの「話したい」「聞きたい」「でも恥ずかしい」「失敗したらどうしよう」という気持ちに寄り添い、一緒に試行錯誤できる関係でありたいという、スタッフたちの考え方の傾向を感じました。
もちろん、ナナメの関係としての、ちょっと先の人生の話をしたり、スタッフの多様性を生かしたりした雑談も、引き続きしていきます。
参加するこどもたちもスタッフも変化する中で、完璧なテンプレートや方法はないでしょう。これからも、学生も子どもも安心できる「できる〜む」をつくるために、ケース会議と研修を重ねていきます。
以下のプロジェクトページでは、ギフテッドプロジェクトsprinGが取り組んでいるその他の保護者の方向けの支援などもご紹介しています。
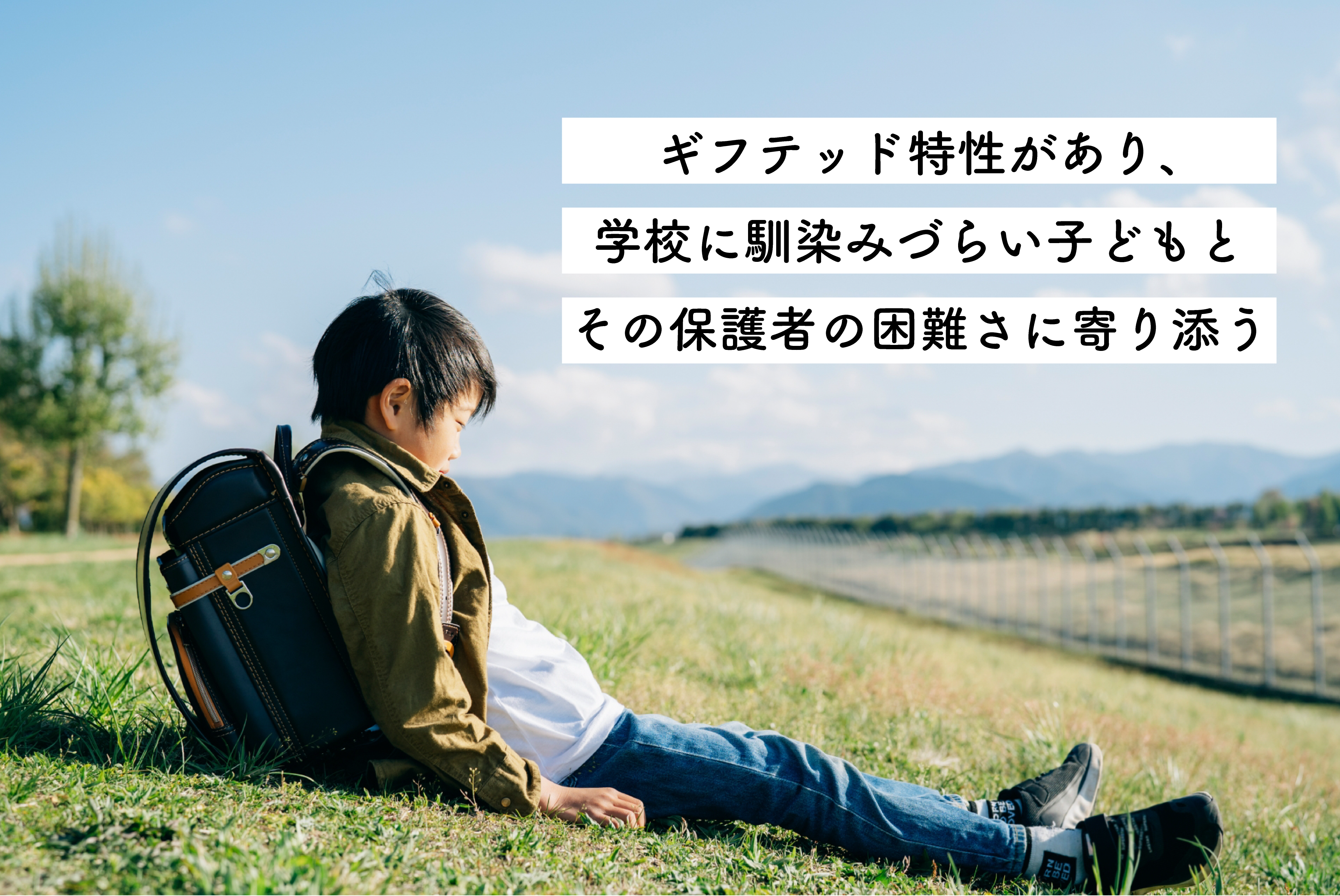
今後とも、学校に馴染みづらく困難を抱えているギフテッドの子どもやご家族の役に立てる活動の実践に努めてまいりますので、ぜひご注目いただけましたら幸いです。