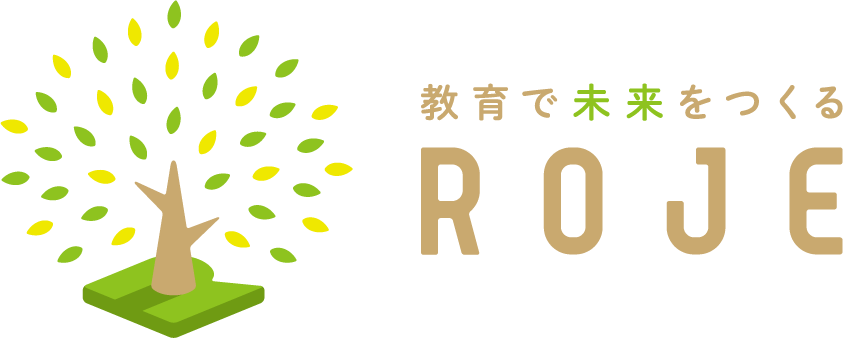2005年に団体が発足し、2007年2月に法人設立しました。以来、活動に賛同する大学生とともに、教育と向かい合っています。
| 2005.10 | 団体発足
虎ノ門パストラルホテルにてNPO発起講演会の開催 |
| 2006.5 | 第一回東京大学五月祭講演会イベント開催(来場者:650人)
・隂山先生、横山先生の授業実践 ・NPO法人FTEXTのワークショップ |
| 2006.8 | 第一回教育夏まつり開催(来場者:400人) |
| 2006.11 | 第一回早稲田祭イベント開催(来場者:350人) |
| 2007.2 | NPO法人登記完了 |
| 2007.5 | 第二回東京大学五月祭講演会イベント
「僕たちの教育再生会議」開催 |
| 2007.7 | 学校ボランティアプロジェクト、事業化 |
| 2008.3 | 関西支部、発足 |
| 2008.5 | 【関東】
東京大学五月祭教育フォーラム2008 「みんなでつくる教育2.0」を開催 隂山メソッド指導者養成講座、開催 |
| 2008.6 | 教育夏まつりプロジェクト、発足 |
| 2008.7 | KIDS SAVER運動への参加 |
| 2008.8 | 「教育夏まつり2008」参加
早稲田祭プロジェクト、発足 教育サマーセミナー2008、開催 |
| 2008.11 | 早稲田祭2008
トークイベント「それでいいのか?大学生!」開催 野口塾 in 東京、開催 |
| 2009.3 | 【関西】
理科実験教室プロジェクト トークカフェプロジェクト 教育夏祭り関西企画プロジェクト、発足 |
| 2009.4 | 【関東・関西】
EDUPEDIA、事業化 サイト開設 |
| 2009.5 | 【関東】
東京大学五月祭教育フォーラム2009、開催 「いま必要な学びとは?」 |
| 2009.8 | 教育夏まつり2009、開催 |
| 2010 | 広報の一環としてリレー対談スタート |
| 2010.3 | 教育スプリングセミナー
「言語力を育成する教育とは」開催 (江戸川区総合文化センターにて) |
| 2010.5 | 【関東】
東京大学五月祭教育フォーラム2010、開催 「学校大公開時代」 【関西】 関西教育プレフォーラムプロジェクト、発足 |
| 2010.11 | 【関西】
立命館にて、関西教育フォーラム2010 開催 関西教育プレフォーラムプロジェクト改め、 関西教育フォーラムプロジェクトとして活動開始 |
| 2011.5 | 【関東】
東京大学五月祭教育フォーラム2011 「教育×震災~いま、私たちができること~」開催 |
| 2011.8 | 【関東・二本松プロジェクト】
教育夏祭り in石巻、開催 (東北の教育復興の一助として) |
| 2011.11 | 【関西】
京都大学にて関西教育フォーラム2011、開催 |
| 2012 | 【関東】
中高まなびプロジェクト、発足 |
| 2012.4 | 学校ボランティアプロジェクト
2012年度中央ろうきん助成金 『応援します!個性が輝く“ひと・まち・くらし”づくり』獲得 |
| 2012.5 | 第五回京都21世紀教育創造フォーラム
『日本の未来と人づくり~グローバル時代のサイエンス教育像~』 京都21世紀教育創造フォーラム実行委員会・関西プレスクラブ、共催 東京大学五月祭教育フォーラム2012 「教育×家庭~皆で支える家庭教育~」開催 屋台プロジェクト2012 「じゃがバター屋台プロジェクト」を開催 |
| 2012.6 | 【関西】学習支援ボランティア開始 |
| 2012.7 | 【関西】TFJとの共催イベント |
| 2012.8 | 東京スタディツアー2012
「絆×未来 福島の子どもたちが、東京で絆と未来を考える」開催 |
| 2012.9 | リレー対談プロジェクト化 |
| 2012.11 | 関西教育フォーラム2012、開催 |
| 2013.1 | 【関西】
EDUPEDIA、参加 放課後ボランティアプロジェクトcomp、発足 イベント企画VARY、発足 |
| 2013.5 | 東京大学五月祭教育フォーラム2013
「教室の今と未来~いじめ・発達障害の視点から~」開催 |
| 2013.8 | 教育夏まつり2013 in二本松
「未来のこたえを、二本松から」 |
| 2013.11 | 【関東】
リレー対談から教育対話プロジェクトに改名 【関西】 関西教育フォーラム2013、開催 |
| 2014.1 | 教育対話プロジェクト配置換、プロジェクト運営部の一事業へ |
| 2014.3 | ROJE復興支援事業in飯館村、発足 |
| 2014.5 | 東京大学教育フォーラム2014
「『グローバル化時代』の日本の教育~変わる世界で、変える人に~」 開催 |
| 2014.8 | 東京スタディツアー2014
「つぼみプロジェクト~3日間の「夢」さがし~」開催 |
| 2014.9 | つぼみプロジェクト、事業化(単発事業から継続事業へ) |
| 2014.11 | 関西教育フォーラム2014
「グローバル化×人材」開催 |
| 2015 | 【関西】
中高まなびプロジェクト、発足 |
| 2015.5 | 東京大学五月祭教育フォーラム2015
「21世紀の教育格差」開催 |
| 2015.8 | つぼみプロジェクト・2015年度東京スタディツアー、開催 |
| 2015.11 | 関西教育フォーラム2015
「教育格差」開催 |
| 2016.1 | 九州支部、正式発足
(2015年度よりEDUPEDIA運営に参加) |
| 2016.5 | 東京大学五月祭教育フォーラム2016
「学校の役割を問いなおそう-公教育が「商品」に!?-」開催 |
| 2016.7 | 【九州】
たんぽぽプロジェクト、発足 |
| 2016.8 | つぼみプロジェクト・2016年度東京スタディツアー、開催 |
| 2016.9 | 東京キワニスクラブ 青少年教育賞 最優秀賞 受賞 |
| 2016.11 | 関西教育フォーラム2015
「いじめ」 |
| 2017.5 | 東京大学五月祭教育フォーラム2017
「大学入試改革!問われる新たな能力 ~現場と家庭は何をすべきか~」開催 |
| 2017.8 | つぼみプロジェクト2017年度東京スタディーツアー、開催 |
| 2017.11 | 関西教育フォーラム2017
「AI時代の教育」 |
| 2018.5 | 東京大学五月祭教育フォーラム2018
「教員の多忙化」 |
| 2018.7 | つぼみプロジェクト2018年東京スタディーツアー、実施 |
| 2018.11 | 関西教育フォーラム2018
「学校×塾×家庭 その子らしさを引き出す新時代の教育」 |